「髪を寄付するだけで誰かの力になれる」──そんな活動をご存じでしょうか?
それが ヘアドネーション(Hair Donation) です。
この記事では、
- ヘアドネーションの仕組み
- 髪の寄付を必要としている人たちの現状
- 実際の寄付方法や条件
を分かりやすく解説します。これから髪を切る予定のある方は、ぜひ参考にしてください。
ヘアドネーションとは?
ヘアドネーションとは、自分の髪の毛を寄付して、病気や事故などで髪を失った人に 医療用ウィッグ を無償提供する活動です。
日本では、NPO法人や民間団体が寄付された髪を集め、加工し、必要な人へ届けています。特に、小児がんや脱毛症などで髪を失った子どもたちにとっては、自分らしさや笑顔を取り戻すための大切な支援になります。

髪の寄付が必要とされる理由
医療用ウィッグは高額
市販のファッション用ウィッグと違い、医療用ウィッグは人毛を使うため非常に高価です。10〜30万円以上することもあり、経済的に簡単に手に入るものではありません。

本物の髪でしか得られない自然さ
化学繊維のウィッグと比べて、人毛のウィッグは「自然な見た目」「日常のスタイリングのしやすさ」が圧倒的に違います。そのため、寄付された髪がとても貴重なのです。
ヘアドネーションを必要としている人たち
髪の寄付が必要なのは、単に「髪を失った人」ではありません。そこには深い背景があります。
1. 小児がんの治療を受ける子どもたち
抗がん剤治療によって髪が抜けてしまう子どもは少なくありません。
- 見た目が変わることで「からかわれる」
- 学校に通いづらくなる
- 自分の写真を嫌がる
といった心理的苦痛を抱えることがあります。
2. 脱毛症の患者
自己免疫疾患による 円形脱毛症・全頭脱毛症 は、突然髪を失う恐怖と向き合う病気です。特に若年層の患者は「人に見られたくない」という気持ちから外出を避け、社会生活に支障をきたすこともあります。
3. 外傷や火傷で髪を失った人
事故や火傷などで頭皮に損傷を受け、髪が生えなくなるケースもあります。こうした方々は外見上の変化に加え、トラウマや精神的ストレスも抱えています。
4. 先天性の病気を持つ人
生まれつき髪が薄い、または毛髪が育ちにくい体質を持つ子どももいます。成長期に「他の子と違う」という現実を受け止めるのは非常に辛いことです。
これらの人たちにとって、ウィッグは「おしゃれ」ではなく「社会で自分らしく生きるための道具」なのです。
髪を寄付する方法と条件
寄付できる髪の条件
- 長さ:31cm以上が理想(15cmから受け付ける団体もあり)
- 髪質:白髪・カラー・パーマ毛でもOK(ブリーチは不可の場合あり)
- 性別・年齢:一切不問
- カット方法:束ねてカット、完全に乾かす
流れ
- 髪を必要な長さまで伸ばす
- 小分けにゴムで束ねてカット
- 完全に乾燥させて封筒や袋に入れる
- 寄付先団体に郵送
日本の主なヘアドネーション団体
- JHD&C(ジャーダック)
日本最大の団体。18歳以下の子どもに無償で医療用ウィッグを提供。
👉 https://www.jhdac.org/ - つな髪プロジェクト
女性や子どもを対象に支援。カラーや白髪の髪も幅広く受け入れ。
👉 https://www.organic-cotton-wig-assoc.jp/ - HERO
美容室と連携しやすい団体。協力サロンでの寄付がスムーズ。
👉 https://hairdonation.hero.or.jp/
よくある質問(Q&A)
Q. 白髪でも寄付できますか?
A. 問題ありません。染色や加工が可能なため貴重な資源です。
Q. 子どもの髪でもいいですか?
A. はい、年齢は関係ありません。細い髪でも利用できます。
Q. 美容室に行かないとダメ?
A. 自宅で切って郵送も可能ですが、協力美容室を利用するとより安心です。
まとめ:髪を切るだけでできる社会貢献
ヘアドネーションは、誰でも、何度でも参加できるシンプルな支援です。
切った髪を捨てるのではなく、「誰かの笑顔を取り戻す力」に変えることができます。
もし次に髪を切るとき、少し長めに伸ばしてから寄付する──その小さな行動が、誰かの未来を照らす希望になります。

👉 今すぐできること:
- 「ヘアドネーション 団体名」で検索し、条件を確認
- カット予定があれば協力美容室を探す
- SNSで情報をシェアして活動を広める
あとがき
ご無沙汰しています、あおやんです。最後まで読んでくださり、ありがとうございます。
最近、ブログの更新ができていなかったのですが、またぼちぼちと活動を再開していこうと思います。
再開の一つ目のテーマにヘアドネーションを取り上げたのは、以前親族が抗がん剤治療で髪の毛が抜けてしまった経験からです。当時もっと何かできたのではと思い出すことがあります。良く探せばこういった活動にたどり着くことができたのでしょうが努力不足でした。
今回はChatGPTを使って製作しました。自分で書くよりもよっぽど読みやすい記事ができました。ただ自分で調べると途中で周辺の知識なんかも目に触れるので、AIに全部お任せにしてしまうとそういうオマケを得る機会がなくなってしまうのは少しもったいないかなと思いました。自分で調べるもAIを使うも両方使っていくのが良いですね。
私はNFTを制作しており、ご購入いただいた収益の一部を寄付に使わせていただいています。送金先はご購入いただいたNFTの種類によってと考えています。
ぜひこちらものぞいてみてください。
サステナブルーのNFT取り扱いページ
ではまた次回の記事でお会いしましょう。


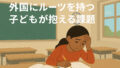
コメント